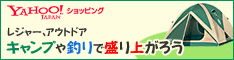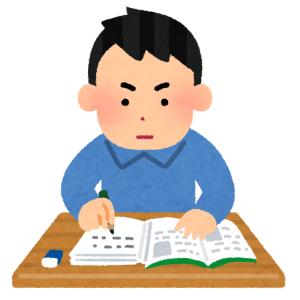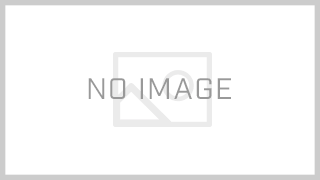こんにちは、toshiです。
今回は心理療法の一つである、フォーカシングについて解説していきたいと思います。
フォーカシングとは?
フォーカシングとは、心理療法の一つです。日本フォーカシング協会によると、
フォーカシングとは、まだ言葉にならないような、からだで感じられる微妙な感覚に注意を向け、そこから言葉を出していく作業です。
フォーカシングを学ぶことで、
自分自身の気持ちをよりよく理解できるようになったり、何か決断をしないといけないときに納得のいく決断が容易になったりします。また、カウンセリングや心理療法を学ぶ際に、カウンセラー自身の訓練として使用することもできます。文章を書いたり、芸術的な作品を生み出す際に、自分の実感がうまく表現できているか確認することに使うこともできます。
とされています。
クライエントが自分の気持ちをより理解できるようになったり、カウンセラー自身の訓練に用いられたり、自分の作品にしっかり反映されているか確認することなどに使用することができるようです。
フォーカシングの始まり
フォーカシングは臨床心理学者のユージン・ジェンドリンが開発しました。
元々、ジェンドリンは哲学者だったのですが、ロジャーズと共同研究していく中で気持ちを言語化するのが難しい人がいることに気づきます。
言語化する前の段階に着目し、無意識的に感じている身体の感覚に焦点を当てていくことで言語化が促進されることを見つけました。
そして、そのまだ言葉にならない感覚をフェルト・センスと呼びます。
そのフェルトセンスに注意を向けることで言語化されていきます。
その際に、その感覚をぴったり表す言葉、ハンドルを探してそれがフェルトセンスをしっかり表現できているのかを突き合わせていきます。それがピッタリであればそのままでいいですし、違うのであればまたそのハンドルを探していきます。この作業を繰り返していくことでフェルト・シフト、「ピッタリだ!」という感覚が得られます。
つねにフォーカシングをしなければならないわけではありません。
フォーカシングで重視されているのは、クライエントとの関係性、その上で傾聴する、それでも感情が上手く出てこない場合はフォーカシングを行います。
つまり、フォーカシングはあくまでカウンセリングでしっかりクライエントが感情を表すための補助技術です。むしろ、クライエントがしっかり感情表出できているのであれば、無理にフォーカシングを行う必要がありません。クライエントの中でフォーカシングが起きているということになるからです。
フェルトセンス
フェルトセンスとは、はっきりした感情ではなく、「なんとなく」感じられていて、意味が含まれているものです。
例えば、「この映画好きだな」という人に、「どんなふうに好きなの?」と聞くと、「なんとなく」という答えが返ってくる。
その「なんとなく」というのは、ちゃんと意味が含まれていて、明確な言葉にまだなっていないのです。「なんとなく」には意味が含まれているのです。
感情
逆に、感情はとても明確で、「怒っている」「不安だ」「うれしい」など、そこには一つの意味が焦点化されている。それらは感情だけを大きく見ているのでなかなか、そこを掘り下げても他のことには目を向けにくい。
「どんなふうに怒っているのか」「どんなふうに不安になっているのか」そういうふうに感情の奥にあるものに目を向けてもらうことで「傷ついたから」とか「「試験に受かるかどうか心配で」とか感情に含まれていたことが明確になっていきます。
こうやって感情から距離をとりつつ、フェルトセンスを取り扱っていくことでクライエントが言語化していなかったことを言葉にしていくことを促していきます。
そうすることで、クライエント自身が気づきを得たり、過去のことの捉え方が変わったりしていきます。
まとめ
フォーカシングは心理療法の一つ
基本は傾聴だが、クライエントが感情から離れていけば、意識的にフォーカシングを行う
まだ言葉にならない感覚をフェルトセンスという
しっくりくるものをハンドル、「ピッタリだ!」となった状態をフェルトシフトという
感情は単一で、そこに含まれる意味が分かりにくい
感情の周りに目を向けることでフェルトセンスをつかむことができる
クライエントの気づきや捉え方の変化を促す
以上まとめです。最後までお読みいただきありがとうございました。
以下、日本フォーカシング協会のリンクを貼っておきます。
また、参考にした文献です。とても読みやすいです。